相続税を少しでも安くしたい」と考える方にとって、不動産への組み換えはとても魅力的に映ります。
特に「アパートを建てれば相続税が減る」という話を聞くと、「それなら…」と前向きになる方も多いのではないでしょうか。
しかし実際は、そのアパート経営が原因で資産を減らしてしまう人が少なくないのです。
今回は、相続税対策としてのアパート経営がなぜうまくいかないのか、注意すべきポイントとともにお伝えします。
なぜアパート経営が相続税対策として注目されるのか?
相続税対策が必要になるのは、株・現金・土地など多額の資産を保有している方です。
これらの資産を現金から不動産へ組み換えることで、相続税評価額を抑えることができるため、アパートやマンションの建築が注目されています。
不動産に組み換えるメリット
例えば、1億円の現金をそのまま相続すると、相続税率50%の場合、5,000万円の税金がかかります。
一方で、1億円でアパートを建てた場合、不動産の評価額は一般的に市場価格の6~8割(6,000万~8,000万円)に抑えられます。さらに「貸家建付地」として土地の評価額も下がるため、現金で相続するよりも相続税を大幅に減らすことが可能になります。
節税効果の具体例
- 現金1億円 → 税額 約5,000万円
- アパート建築で評価額6,000万円 → 税額 約3,000万円
このように、評価額を抑えるだけで2,000万円の節税効果が期待できます。
アパート経営が失敗する4つの理由
相続税対策として魅力的に見えるアパート経営ですが、9割以上が失敗しているとも言われています。
その主な原因は、節税効果ばかりに目が向き、経営そのものが成り立っていないケースが多いためです。
主な失敗パターン
- 空室リスク:立地や賃貸需要を見誤り、入居者が集まらない
- 建築費の割高:相場より高額な建築費で初年度から赤字
- 大家業の知識不足:クレーム対応や修繕、税務処理に苦戦
- サブリースの落とし穴:数年後に家賃減額などの不利な契約変更
どれも「節税になるから建てた」だけでは避けられないリスクです。
まとめ:節税目的だけでは危険!経営者マインドが必要
アパート経営は、相続税対策として有効な手段のひとつですが、「建てたら終わり」ではなく、「建ててからが始まり」です。
税金対策に目を奪われるあまり、経営計画が甘いと、節税どころか資産を減らす結果にもなりかねません。
アドバイスを挙げるとすると
- 節税だけでなく、長期的な経営の視点を持つ
- 事前に市場調査・事業計画・出口戦略を立てる
- 専門家(税理士・不動産鑑定士・FP)に相談する
- 自分が「経営者」になる覚悟を持つ
などといったスキルが、最低限必要となります。
結論
相続税を減らしたいから…というだけの理由でアパート経営に手を出すのは非常に危険です。
アパート経営は、長期的に責任を持って向き合う「事業」であることを忘れずに判断しましょう。
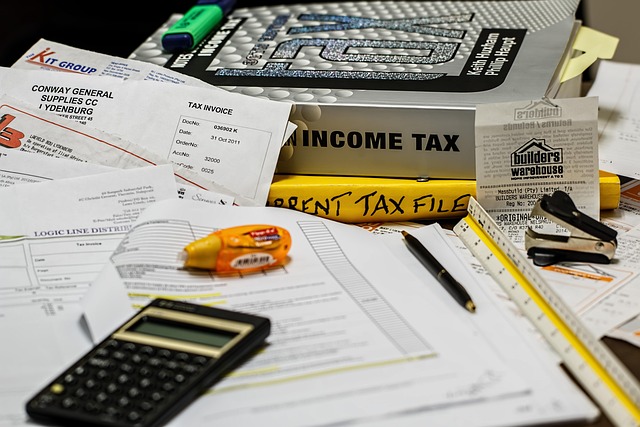


コメント